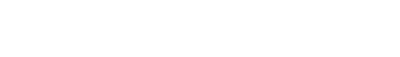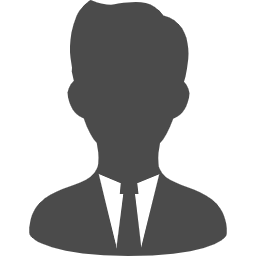
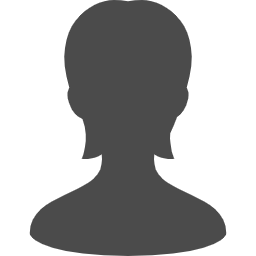
という疑問をお持ちではありませんか?
賃貸物件の地震被害は、オーナー(物件の所有者)負担で修繕するのが原則ではあるものの、借り主に負担が発生する場合もあるので注意が必要です。
必要な知識を身につけて、地震が発生する前に、可能な対策を行っておきましょう。
この記事では、
- 地震で賃貸物件が損傷した場合の費用負担
- 住めなくなった場合の契約関係
- 特に注意が必要なケース
について解説します。
万が一の地震被害に備えて、ぜひご一読ください。
地震で賃貸物件に損害が発生した時の費用負担

地震で賃貸物件が損傷した場合、基本的には
- オーナー(物件の所有者)の負担する費用:建物の修繕費用
- 借り主の負担する費用:自身の家財道具の修理・買い替え費用
となることが一般的です。
ただし、例外もあるので注意が必要です。
オーナーと借り主それぞれの負担について、詳しく見ていきましょう。
オーナー(物件の所有者)が負担する費用
オーナーが負担するのは、主に建物本体の修繕費用です。
民法606条により、オーナーは、入居者が賃貸物件を使用するために必要な修繕をする義務を負うことが定められているからです。
具体的には、「地震により生じた建物のヒビ」、「窓ガラスの割れ」、「扉の歪み」などが修繕の対象となります。
地震によって建物が損傷した場合、オーナーには、借り主が生活に支障をきたさないよう、建物を修繕する責任があるのです。
ただし、借り主の過失によって損害が発生した場合は、借り主の負担で修繕する場合もあります。
例えば、
- 倒れやすい家具を窓ガラスのそばに置いていた
- 禁止されたスペースで火器を使用していたため、火災が発生した
といった場合です。
借り主が負担する費用
一方、借り主は自身の家財道具の損害や、けがの治療費を負担しなければなりません。
地震で家具が壊れたり、地震によりけがをしたりした場合も、基本的には自己負担となります。
ただし、これらの損害が発生したことについて、オーナー側に責任がある場合、家財の買い替え費用や治療費についてもオーナーに請求できる場合があります。
例えば、「建物が老朽化しているなどで、オーナーに修理依頼していたにも関わらず、オーナーが適切な対応を怠ったため、損害が生じた場合」などが該当します。
地震による損害は、状況によって、補償する費用をどちらが負担するかが変わってくるので注意が必要です。
賃貸物件が地震で損傷した場合の契約は?

次に、地震で賃貸物件が損傷した場合、賃貸借契約がどうなるのかについて見ていきましょう。
- 建物が倒壊して住めない場合
- 賃貸物件の設備が壊れた場合
それぞれ解説します。
倒壊して住めない場合
地震により、建物が倒壊して住めなくなった場合、賃貸借契約は自動的に終了します。
賃貸物件が使用できなくなった場合、契約が終了することが、民法616条の2により規定されているからです。
この場合、借り主の家賃の支払い義務はなくなります。
さらに、通常の解約とは異なるため、短期解約等による違約金も発生しません。
敷金も返還されますが、借り主の過失による損害がある場合は、その分が差し引かれる可能性があります。
なお、引っ越し費用は借り主の負担となります。
設備が壊れた場合
地震で賃貸物件の設備が壊れたり、設備の一部が使用できなくなったりした場合は、借り主はオーナーに修理を求めることができます。
例えば、地震により、賃貸物件の給水設備が損傷し、トイレやシャワーが使えなくなったような場合が該当します。
なお、修理に時間がかかる場合、修理期間中の家賃は、故障部分に応じて減額されます。
減額割合は、契約によっても異なりますが、以下の割合を参考にすると良いでしょう。
家賃の減額の計算式
【計算例】月額賃料 100,000 円で、ガスが 6 日間使えなかった場合
月額賃料100,000 円 ✕ 減額割合10% ✕ ( 6 日-免責日数 3 日 )/月 30 日=1,000 円の賃料減額 ( 1 日あたり約 333 円 )
状況による減額割合と免責日数
| 状況 | 減額割合 | 免責日数 |
| 電気が使えない | 40% | 2日 |
| ガスが使えない | 10% | 3日 |
| 水が使えない | 30% | 2日 |
| トイレが使えない | 20% | 1日 |
| 風呂が使えない | 10% | 3日 |
| エアコンが作動しない | 5000円(1ヶ月あたり) | 3日 |
| テレビ等通信設備が使えない | 10% | 3日 |
| 雨漏りによる利用制限 | 5〜50% | 7日 |
(参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」)
賃貸物件の地震で特に注意が必要なケース

地震で賃貸物件に被害が出た場合、状況によっては、特に注意が必要なケースがあります。
ここでは、以下の2つについて説明します。
- 築年数が古い場合
- 地震保険に加入していない場合
それぞれ見ていきましょう。
築年数が古い場合
賃貸物件の築年数が古い場合、物件の耐震性が低くなっている可能性が高いため、注意が必要です。
例えば、以下の表は、建築基準法の耐震基準が変更された年月をまとめたものです。
| 法律の制定年月 | 名称 | 耐震性 |
| 1950年11月 | 旧耐震基準 | 中規模地震(震度5程度)でほとんど損傷しない |
| 1981年6月 | 新耐震基準 | 大規模地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊の恐れがない |
| 2000年6月 | 現在の耐震基準 | 現在の耐震基準 大規模地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊の恐れがない 「限界耐力計算」の義務付け |
特に、1981年以前に建築された物件については、現在よりも耐震性が著しく低くなっていることが分かります。
賃貸物件の耐震基準は、建築された当時の耐震性を満たしていれば違法とはならないものの、老朽化等により、耐震性を満たさなくなっていると判断されるケースもあります。
万が一、耐震基準を満たしていない物件が倒壊し、入居者や近隣住民に被害が出ると、オーナーの責任となってしまう場合もあるため、耐震診断を行うなどの対策を検討しましょう。
地震保険に加入していない場合
地震保険に加入していない場合も、注意が必要です。
地震により生じた損害は、通常の火災保険では補償されないからです。
例えば、火災により損害が生じた場合でも、火災が地震を原因として発生したのであれば、火災保険の対象にはなりません。
そのため、オーナー・借り主いずれの立場であったとしても、自分が負担する費用があれば、全額自費で支払わなければならなくなります。
特に建物が、前述の「築年数が古い物件」に該当する場合は、地震による倒壊・損傷リスクも高くなるため、地震保険へ加入することも検討してみましょう。
賃貸物件で地震トラブルの不安がある場合、弁護士に相談するのがおすすめ
この記事では、
- 地震で賃貸物件に損害が発生した場合の費用や契約
- 賃貸物件の地震について、特に注意が必要なケース
についてお伝えしました。
賃貸物件の地震対策では、事前の備えが最も重要です。
オーナー・借り主双方が、事前にできる対策を行っておくことで、地震による被害を最小限におさえることができるからです。
とはいえ、賃貸物件の地震トラブルでは、法的な知識や対応が必要となるケースも多いです。
もしも不安や疑問に思っている点がある場合は、地震が発生する前に、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
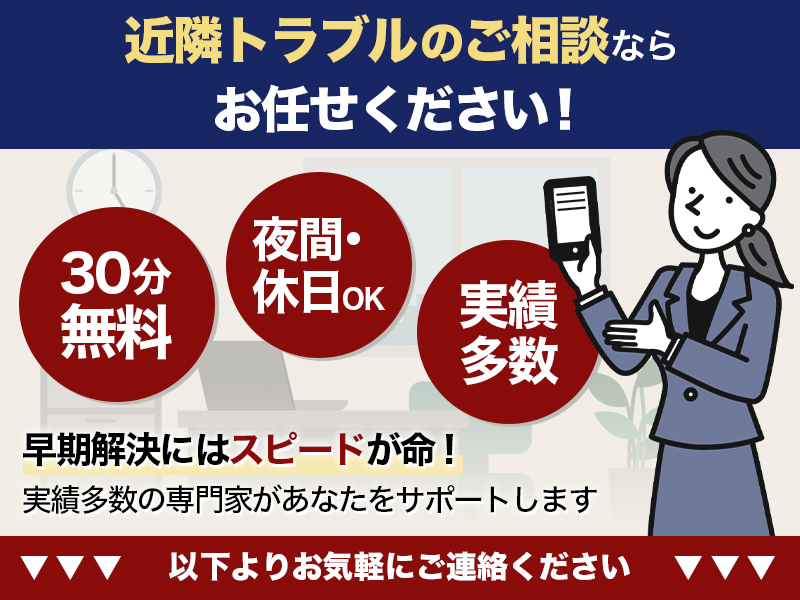
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。