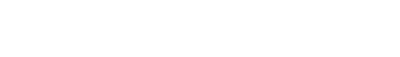突然、家賃の値上げを告げられると、「違法じゃないの?」と感じてしまうものです。
実際、家賃の増減は法律で一定のルールが定められており、正当な理由があれば認められています。
一方で違法となるケースが存在するのも事実です。
そこで本記事では、家賃値上げが合法か違法かを見分けるポイント、契約更新時に注意すべき点について詳しく解説します。
貸主側からの違法な値上げ、不当な主張に振り回されないための知識を身につけましょう。
家賃値上げが認められる法律上の根拠とは

結論から言えば、家賃の値上げは貸主側の自由ではありません。
実際には「借地借家法」などの法律によって、一定の制限が設けられています。
まずは、家賃改定に関する基本的なルールについて整理してみましょう。
借地借家法第32条に定められた3つの条件
借地借家法32条1項では、貸主が家賃を増額できる条件として、「土地や建物にかかる税負担の増加」「経済事情の変動」「近隣相場との比較」を挙げています。
●借地借家法第32条1項
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
(引用:借地借家法|e-Gov 法令検索)
これらの要件を満たさない、つまり単なる思いつきの値上げは、法律上の正当性を欠いたものです。
仮に裁判にまで発展すれば、無効と判断される可能性があります。
よって、家賃の値上げを提示されたからといって、即座に受け入れる必要はありません。
値上げ請求の正当性を証明するのは貸主側
家賃の値上げにおいて重要なのは、「正当性を証明する責任は貸主にある」という点です。
借主が「納得できない」と拒否した場合、貸主は「税金がこれだけ上がった」「近隣相場はこれくらい」といった具体的な資料を提示しなければならないのです。
もし裁判に発展した場合も、裁判所は周辺の賃料相場や建物の維持費などを総合的に判断し、増額の妥当性を判断します。
なお、家賃の値上げを請求されたからといって借主が不利になるわけではありません。
具体的には、設備の故障が起きた際に対応してもらえない、退去時に敷金が戻ってこないといったことはなく、法律上しっかり保護されているのでご安心ください。
違法とされる家賃の値上げ3つの具体例

家賃の増額請求自体は法律で認められていますが、すべての請求が認められるわけではありません。
借地借家法における増額の条件から外れていたり、借主に不当な不利益を与えたりするような値上げは、「違法」と判断される可能性があります。
例1:契約期間中に一方的に変更を迫る値上げ
賃貸借契約では「契約期間中の賃料額」が明確に定められています。
たとえば、「2年間は月額8万円」と合意している場合、その期間内に貸主が一方的に「来月から9万円に上げます」と通告しても、これは契約違反であり無効です。
例2:借主を追い出す目的での値上げ
家賃の増額を利用して、借主を事実上退去させようとする行為も違法とされます。
たとえば、「正当な退去理由がないため、代わりに払えないほどの高額家賃を提示する」といったケースです。
過去の裁判例を見ても、裁判所はこうした不当な値上げを「退去強要」とみなし、借主の居住権を守る立場を取るケースが多く見られます。
例3:近隣相場から大きく乖離した値上げ
家賃の増額が正当とされるかどうかは、「近隣の家賃相場」との比較が大きな判断材料です。
たとえば、周辺の同条件の物件が月額8万円前後なのに対し、貸主が「12万円に上げる」と一方的に請求した場合、正当性を欠くとして違法とされる可能性があります。
違法と思われる家賃の値上げに対して、交渉のポイントや断り方をこちらの記事で紹介しています。
-

-
家賃の値上げは拒否できる?断り方や交渉のポイント、応じないとどうなるかを解説
貸主から「来月以降の家賃を値上げしたい」と連絡がくれば、拒否したいと感じるのが普通です。 家賃の値上げは生活に直結するため、簡単に応じられるものではありません。 しかし、「応じる義務があるのでは?」「 ...
続きを見る
契約更新時の家賃値上げと法律上のルール

通常、家賃の値上げは契約更新の場面で提示されるケースがほとんどです。
ただし、更新方法は大きく「合意更新」と「法定更新」があり、それぞれ扱いが異なるため注意が必要です。
合意更新と法定更新の違い
通常、賃貸借契約の更新は、貸主と借主双方が条件を話し合って合意する「合意更新」によって行われます。
この場合、貸主は更新時に「新しい家賃額」を提示できますが、借主が納得しなければ契約条件は成立しません。
合意が前提となるため、話し合いで合意に至らなければ従前の契約条件が維持されるか、更新自体が行われないということになります。
一方、借地借家法第26条1項で定められているのが「法定更新」です。
●借地借家法第26条1項
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
(引用:借地借家法|e-Gov 法令検索)
簡単にいえば、契約期間が満了しても貸主が「更新しない通知」や「条件変更の通知」を適切な時期(1年前から6か月前まで)にしなかった場合、従前と同一条件で契約が自動的に更新されるというルールです。
契約更新時の値上げには両者の合意が必要
法定更新が適用されると、更新後の契約は「期間の定めのない契約」となり、家賃も以前の金額のまま継続されます。
つまり、貸主が一方的に値上げを主張しても、借主が合意しなければ、従前の家賃がそのまま有効となるのです。
この規定は借主を守るための「強行規定(当事者の意思にかかわらず強制的に適用される法律)」とされており、貸主側の都合だけで更新を拒否したり、値上げを強制したりすることはできません。
したがって、契約更新時の家賃改定は、あくまでも「両者の合意」があって初めて有効になるものだと覚えておきましょう。
こじれた場合は裁判に発展することも
家賃の値上げに同意しなかったとしても、強制退去させられることはありません。
賃貸借契約が有効に続いている限り、貸主が一方的に契約を解除することはできず、退去には「正当な理由」が必要です。
ただし、貸主が納得できない場合には、裁判所へ「賃料増額請求」を申し立てる可能性があります。
裁判では、周辺相場や建物の維持費、経済事情の変化などを踏まえ、適正な家賃額が判断されます。
そのため、「とりあえず拒否しておけば良い」というわけではなく、最終的には客観的な根拠に基づいて、裁判所が最終判断を下すことになるでしょう。
家賃の値上げトラブルは弁護士に相談を
家賃の値上げは、正当な理由がある場合にのみ認められるものであり、納得できない値上げについて無理に応じる必要はありません。契約期間中に一方的に変更を迫られるケースや、不当な目的による値上げは違法と判断されることもあります。冷静に根拠を確認し、不当と感じた場合は毅然と対応してください。
それでも不安が残る場合や、貸主との交渉が難しいと感じる場合には、弁護士への相談をおすすめします。弁護士なら、値上げの妥当性を法的に判断してくれるだけでなく、交渉や裁判対応も任せられるため、不利な条件を押し付けられる心配がなくなります。
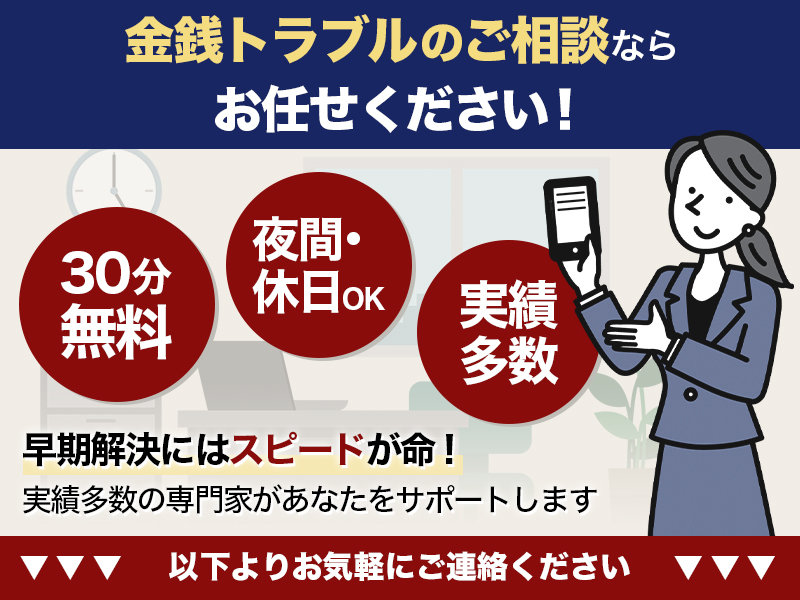
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。