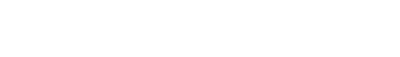配偶者の死後、
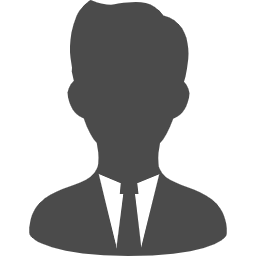
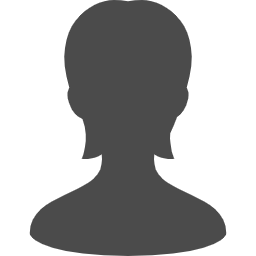
と考える人は少なくありません。
そのような場合、「姻族関係終了届」を提出することで、法的に義理の親族との関係を断つことができます。
この手続きは「死後離婚」とも呼ばれ、介護を断る理由作りやお墓の問題を避ける手段として注目されています。
ただ、遺族年金や相続への影響も気になるところです。
そこで本記事では、死後離婚の手続き方法、事前に知っておきたいポイントについて解説します。
そもそも死後離婚とは?
死後離婚とは、配偶者の死亡後に義理の親族との法的な関係を解消するために行う手続きです。
勘違いされやすいのですが、配偶者と死後に離婚をする手続きではありません。
結婚をすると配偶者だけでなく、相手の親族とも法律上の「姻族(いんぞく)」となります。
配偶者が亡くなった後も義理の両親や親戚との関係が続くことに違和感を覚える方は少なくありません。
そんな場合は、死後離婚をすることで姻族関係が解消され、義理の親族との関係を断つことができるのです。
死後離婚をするメリットとデメリット

では、死後離婚をすることで具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
感情面や経済面を含め、どのような影響があるのかを理解しておくことが大切です。
死後離婚のメリット
死後離婚の具体的なメリットは以下のとおりです。
扶養・同居義務の解消
そもそも、血縁関係のない配偶者側の両親に対して扶養・同居義務が発生することはありません。
しかし、「面倒を見るのが当たり前」といった古い風潮もあり、なかなか断れないのが現実です。
そんなときは、死後離婚によって姻族関係を断つことで、距離を置くための明確な理由を作ることができます。
相手親族から介護や同居の継続を期待されることがなくなり、自分自身の生活を優先できるメリットがあります。
精神的・経済的負担の軽減
「姻族関係終了届」を提出することで、義理の親族との法的なつながりを断つことができます。
これにより、義理の親族からの干渉や親戚付き合いを続ける必要がなくなり、精神的・経済的負担が軽減される点は、大きなメリットといえるでしょう。
自由な供養方法の選択
死後離婚をすることで、配偶者の家のお墓に入ることを避け、自分の希望に沿った供養方法を選ぶことができます。
たとえば、自身の実家の墓に入る、納骨堂を利用する、散骨や樹木葬を選択するなど、多様な供養の中から自由に選択できるメリットがあります。
死後離婚のデメリット
一方で、死後離婚の主なデメリットは以下のとおりです。
義理の親族との関係性の悪化
死後離婚をすることで、義理の親族との関係が悪化する可能性があります。
義両親や親族によっては「家族を捨てた」と受け取られ、感情的な対立が生じることもあるでしょう。
義理の親族と円満に関係を終えたい場合は、慎重に話し合いを進めることが大切です。
遺産分割トラブルのおそれ
死後離婚をしても、配偶者の遺産相続には影響しません。
相続権は婚姻関係に基づくため、たとえ「姻族関係終了届」を提出しても、すでに相続した財産を返す必要はないのでご安心ください。
ただし、義理の親族からすれば、「遺産だけを奪われた」と考える方もいます。
スムーズに遺産分割できないと、トラブルが発生する可能性もあるため注意が必要です。
子どもからの反感
死後離婚によって配偶者側の親族と関係が切れたとしても、子どもの関係まで切れるわけではありません。
死後離婚後であっても義両親は、子どもにとっての祖父母であることに変わりはないのです。
そのため、子どもから反感を買うおそれがある点には注意が必要です。
もし子どもがいるのであれば、理解を得た上で手続きを行うことを推奨します。
死後離婚に伴うよくあるトラブルについては、詳細をこちらの記事で解説しています。
-

-
死後離婚でトラブルに?配偶者の親族との問題や後悔しないための対策
配偶者が亡くなった後、「配偶者の親族と関係を断ちたい」とお考えではありませんか? 自分の生活すら精一杯なこの時代、義両親や義兄弟に対して、「介護や同居をしてあげられるほど余裕がない」のも無理はありませ ...
続きを見る
死後離婚の手続き方法

死後離婚を正式に成立させるためには、「姻族関係終了届」を役所に提出する必要があります。
以下では、死後離婚の具体的な手続きの流れや注意点について解説します。
死後離婚に必要な書類と提出方法
姻族関係終了届を提出する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 姻族関係終了届(市区町村役場の窓口で取得可能)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 届出人の印鑑(市区町村役場によっては不要な場合もあり)
- 戸籍謄本(本籍地が届出先と異なる場合に必要)
姻族関係終了届の提出先は、届出人(手続きを行う人)の本籍地または住所地の市区町村役場です。
役所の窓口に必要書類を持参し、提出すれば即日受理されます。
代理人による届出も可能ですが、その場合は委任状が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
また、郵送での提出を受け付けている市区町村役場もあります。
郵送の場合、必要書類を添えて役所に送付し、受理後に通知が届きます。
ただし、訂正が必要になった場合はやり取りが増えてしまうため、可能であれば窓口で提出するのがおすすめです。
死後離婚する前に知っておきたい3つのこと
死後離婚をする前は、以下の3つのことを知っておくと良いでしょう。
義理の親族の同意は必要なし
姻族関係終了届を提出する際、義理の親族の同意を取る必要はありません。
手続き後に市区町村役場からの通知なども届かないため、相手に知られる心配はないでしょう。
ただし、姻族関係を終了した事実を伝えなければ上述したようなメリットは発生しないため、いずれは伝えなければなりません。
死後離婚に費用はかからない
死後離婚をするのに費用はかからないのでご安心ください。
届け出をする市区町村役場と本籍地が異なる場合のみ、戸籍謄本の取得費用として「450円」が必要になります。
死後離婚はそれほど難しい手続きではないため、弁護士などの専門家に依頼する必要はないでしょう。
しかし、書類の提出だけでなく、義両親への連絡などに負担を感じる場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士が代理で連絡をしてくれるため、精神的な負担を感じることなく、義両親側との関係を断つことができます。
名字は自分の意思で選択可能
死後離婚をしても、婚姻時の名字をそのまま使うことが可能です。旧姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出しなければならない点に注意しましょう。
子どもの名字も変更したい場合は、家庭裁判所からの許可を得る必要があります。住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行ってください。
死後離婚後に確認すべき手続き

死後離婚の手続きを終えた後も、いくつかの手続きを確認しておく必要があります。
特に、金銭面や生活設計に関わる部分については慎重に対応しましょう。
遺族年金の受給には影響なし
姻族関係終了届を提出しても、遺族年金の受給資格には影響がありません。
請求する際は、市区町村役場に必要書類を持参して手続きを行いましょう。
ただし、再婚すると遺族年金を受け取る権利は失われてしまいます。
死後離婚と直接関係があるわけではありませんが、再婚の予定がある場合は注意が必要です。
相続に関する手続き
死後離婚をしても、配偶者の遺産相続には影響しません。
相続権は配偶者との婚姻関係に基づくものであり、義両親らとの姻族関係を解消した後でも相続権は維持されます。
ただし、まだ遺産分割が終了していない場合、相続の際には義理の親族との話し合いは避けられないため、死後離婚後も一定の関わりが生じる可能性があります。
相続トラブルを避けるためにも、遺産分割協議を円滑に進める工夫が必要です。
なお、配偶者が多額の借金を抱えている場合、死後離婚によって相続を免れるわけではありません。
「相続放棄」や「限定承認」といった手続きが必要なため注意しましょう。
お墓や供養の手配
死後離婚を選択する理由の一つに「配偶者と同じ墓に入りたくない」というものがあります。
その場合、別の供養方法を検討する必要があります。
たとえば、実家のお墓に入りたい場合は、実家の墓地に受け入れ可能かどうかを事前に確認しなければなりません。
永代供養を選択するのであれば、寺院や霊園の永代供養墓を検討しましょう。
なお、死後離婚をすることで、相手の家のお墓を管理する必要がなくなるため、状況次第では墓じまいをしなければならない場合があります。
墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、遺骨を他の供養先に移すことです。
墓じまいについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
-

-
墓じまいはどうやって進める?必要な手続きや費用は?
少子高齢化やライフスタイルの変化により、「墓じまい」を検討する人が増えています。 しかし、「墓じまいにはどのような手続きが必要なのか」「費用はどのくらいかかるのか」など、具体的な進め方がわからず悩む方 ...
続きを見る
死後離婚で新たな人生を歩むために
死後離婚は、配偶者の親族との関係を解消し、自分らしい生き方を選択する方法のひとつです。
しかし、相続や子どもの問題もあるため、慎重に検討することが大切です。
手続き自体は難しくありませんが、親族との関係や供養方法についても考慮しながら進めましょう。
もし手続きやトラブルに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのも一つの選択肢です。
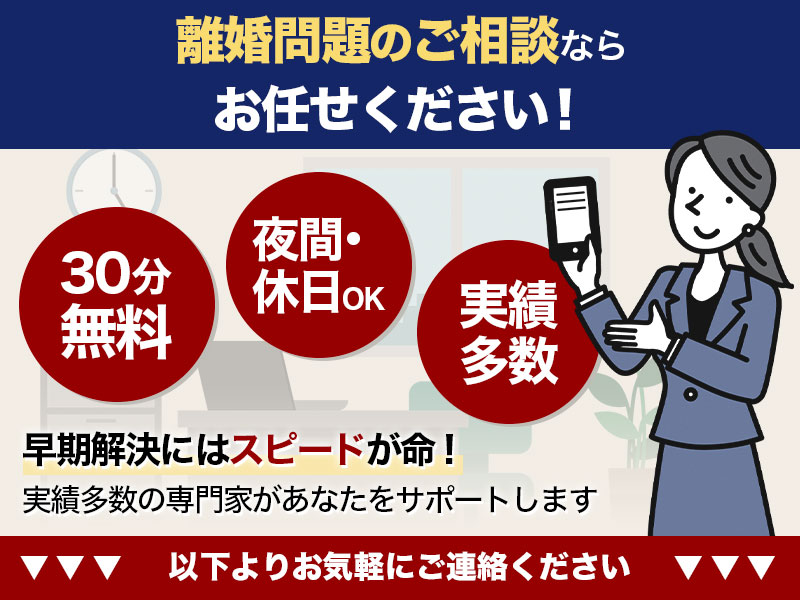
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。