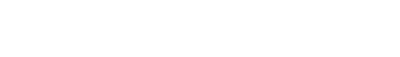配偶者が亡くなった後、「配偶者の親族と関係を断ちたい」とお考えではありませんか?
自分の生活すら精一杯なこの時代、義両親や義兄弟に対して、「介護や同居をしてあげられるほど余裕がない」のも無理はありません。
こうした背景もあってか、近年「死後離婚(姻族関係終了届の提出)」を利用し、配偶者の親族との法的なつながりを解消する方が増えてきました。
しかし、死後離婚を進める中で、思わぬトラブルに巻き込まれるケースもあります。
そこで本記事では、死後離婚で起こりやすいトラブルの具体例や、後悔しないための対策について詳しく解説します。
死後離婚とは?配偶者の親族と縁を切る制度

死後離婚とは、配偶者が亡くなった後に、その親族(義両親や義兄弟姉妹)との法的な関係を解消する手続きです。
正式には「姻族関係終了届」と呼ばれ、これを役所に提出することで、配偶者の親族との法的な関係が終了します。
死後離婚の手続きについては、こちらの記事で詳細を解説しています。
本来、結婚により生じる配偶者の親族との関係は、配偶者が亡くなった後も続きます。
法的に見れば親族としての義務は少ないものの、配偶者の親族から「これまで通りの付き合いを続けるべきだ」と求められるケースもあります。
特に、義両親の介護や法事・お墓の管理など、精神的・経済的な負担が生じる場面も多いでしょう。
そうした中、「配偶者が亡くなった後は、自分の人生を自由に生きたい」と考える方の間で、死後離婚が注目されることになりました。
死後離婚で起こりやすいトラブル事例
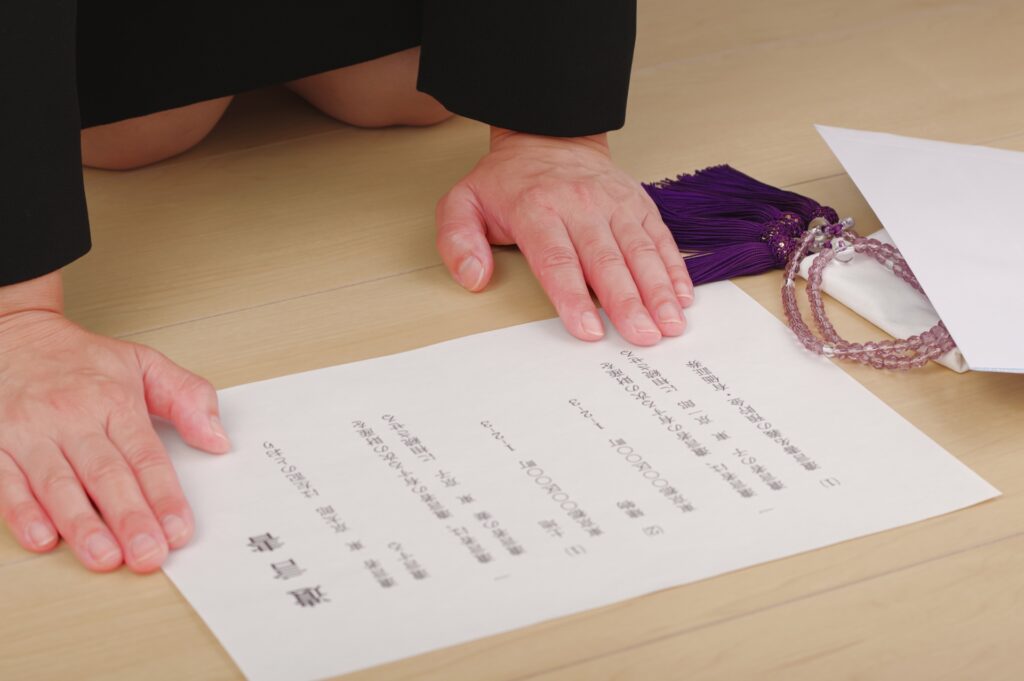
一方で、死後離婚を決意したものの、配偶者の親族との関係や金銭的な問題などが原因で、思わぬトラブルに発展するケースがあります。
特に、配偶者の親族が死後離婚を快く思わない場合、感情的な対立が生じやすく、話し合いがこじれることも少なくありません。
以下では、死後離婚をめぐって起こりやすい具体的なトラブル事例について解説します。
配偶者の親族からの嫌がらせによるトラブル
死後離婚を決めたことに対して、配偶者の親族から嫌がらせを受けるケースがあります。
特に、義両親や義兄弟姉妹から強い反発を受けることがあり、中には執拗な連絡や圧力をかけてくることもあります。
地域柄、慣習などを重んじる家庭では、「死後離婚は恥ずべき行為」と考えられ、批判的な態度を取られることが多いです。


こうした嫌がらせを回避するためには、感情的にならず、あらかじめ関係を整理したい理由を明確に伝えることが重要です。
直接の対話が難しい場合は、弁護士を通じて対応してもらうことで、死後離婚を負担なく行うことができるでしょう。
遺産分割を巡ったトラブル
死後離婚は「姻族関係」を解消する手続きであり、配偶者の相続には影響しません。
しかし、配偶者の親族が「死後離婚するなら、遺産を受け取る資格はない」と主張し、トラブルになることがあります。
特に、配偶者の親族が相続人に含まれている場合や、財産の分け方について明確な取り決めがない(遺言書がない)場合、遺産分割の話し合いが難航することもあります。
相続争いがこじれると、弁護士を交えた調停や裁判に発展する可能性もあるため、遺産の取り扱いについては事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
遺産を受け取る側としても、「姻族関係終了届を提出すると相続権がなくなるのでは?」と不安に感じますが、死後離婚は相続権が失われるわけではないのでご安心ください。
お墓や供養に関連したトラブル
「配偶者の親族と同じお墓に入りたくない」と考えて死後離婚を選ぶ人は多いですが、墓じまいや改葬(遺骨の移動)を巡ってトラブルが起こることもあります。
特に、すでに配偶者の遺骨が相手の家のお墓に納められている場合、「墓を守るのは嫁(婿)の責任」と考える親族と、意見が対立することがあります。
こうしたトラブルを回避するためには、配偶者の生前に供養の方針を話し合っておくことが理想的です。すでに相手の家のお墓に納骨されている場合は、墓地の管理者や弁護士に相談しながら、改葬や供養の手続きを進めるのが良いでしょう。
墓じまいに関するトラブルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
-

-
墓じまいでトラブル勃発?後悔しないためにできること
墓じまいを進める中で、 親族が反対して話が進まない お寺から高額な離檀料を請求された 墓じまいの費用負担で揉めてしまった などのトラブルに直面していませんか? 墓じまいは、単なるお墓の撤去ではなく、親 ...
続きを見る
遺族年金の受給におけるトラブル
死後離婚をすると、遺族年金が受け取れなくなると勘違いをする方が多いですが、これは誤解です。
遺族年金は、亡くなった配偶者の年金を受け取る権利がある家族に支給されるものであり、「姻族関係終了届」を提出しても、年金の受給資格には影響しません。
しかし、配偶者の親族の中には「死後離婚したのだから、遺族年金を受け取る資格はない」と思い込み、受給をやめるよう求めてくるケースがあります。
遺族年金の受給資格は法律で定められており、親族の意向で支給を止められるものではないのでご安心ください。
子どもからの反感によるトラブル
死後離婚を決めたことで、配偶者の親族だけでなく、実の子どもとの関係がぎくしゃくするケースもあります。


死後離婚をすることで、子どもが親族とのつながりを絶たれることに不満を感じることがあります。
子どもがすでに成人している場合、親の判断を尊重してくれることが多いですが、未成年の子どもがいる場合は、事前に話し合いの場を持つことが大切です。
死後離婚を後悔しないための対策

死後離婚を決意する理由はさまざまですが、勢いだけで進めてしまうと「こんなはずじゃなかった」と後悔することもあります。
以下では、死後離婚を後悔しないために知っておくべき対策について解説します。
死後離婚のデメリットを理解する
死後離婚には、精神的な解放感や法的な関係の整理といったメリットがある一方で、いくつかのデメリットも伴います。
以下にまとめてみましたので、しっかり理解しておきましょう。
届出提出後は取り消しできない
姻族関係終了届を一度出してしまえば、もう取り消すことはできません。後から後悔しても元に戻すことはできないため、慎重に検討する必要があります。
相手のお墓には入れない
配偶者の親族との関係を断ってしまえば、相手のお墓にはもう入ることはできません。
実家にお墓があるなど状況が整っていれば問題ありませんが、自身が亡くなった際のお墓を用意しなければならない点は考慮すべきでしょう。
死後離婚で相続問題は解決しない
亡くなった配偶者に多額の借金があった場合、死後離婚をしても相続には影響がないため、マイナス財産を相続することになります。
マイナス財産を相続したくない場合は、「相続放棄」や「限定承認」といった手続きが別途必要になることを理解しておきましょう。
本来は義両親に対して扶養・同居義務はない
死後離婚を考える理由の一つに、「義両親の介護をしたくない」「配偶者の親族との関係を続けたくない」というものがあります。
しかし、法律上、配偶者の親族(義両親や義兄弟姉妹)に対して扶養・同居義務を負うことはありません。
扶養義務が発生するのは、民法上の「直系血族」または「兄弟姉妹」に限定されるため、たとえ義両親が介護を必要としていても、義務的に負担する必要はないのです。
また、配偶者が生前に「親の面倒を見てほしい」と言っていたとしても、それを守る法的義務はありません。
配偶者が亡くなった後、義両親から「一緒に住んでほしい」と言われた場合でも、自分の意思で断ったとして法的な問題は何も生じません。
死後離婚をしなくても、配偶者の親族と距離を置くことは可能です。
死後離婚を考える前に、現状の関係を見直し、必要な範囲で距離を取る方法についても検討しましょう。
事前に相手親族と話し合いをする
死後離婚は、配偶者や配偶者の親族から許可・同意を得る必要のない手続きです。
よって、事前に話し合いをしないまま進めてしまうと、配偶者の親族が驚き、反発する可能性が高まります。
できる限り、配偶者の生前に供養や今後の関係について話し合うのが理想です。
ただ、感情が高ぶっているときに話し合いをすると、対立が深まりやすいため、冷静なタイミングを見極めなければなりません。
感情的に「縁を切りたい」と言ってしまうと、相手の反発を招くため、なるべく冷静かつ丁寧に伝えることが大切です。
トラブルを回避して納得のいく死後離婚を
死後離婚は、配偶者の親族との関係を整理し、自分らしい人生を歩む手段の一つですが、感情的な対立や手続きの誤解によってトラブルに発展するケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、事前の準備と慎重な対応が不可欠です。
死後離婚のデメリットを理解し、義理の親族と適切にコミュニケーションを取ることで、不要な争いを避けましょう。
もし親族との話し合いが難航したり、法的な問題が発生したりした場合は、一人で抱え込まずに弁護士に相談するのも有効な手段です。
個々の状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、円満な解決が実現できるでしょう。
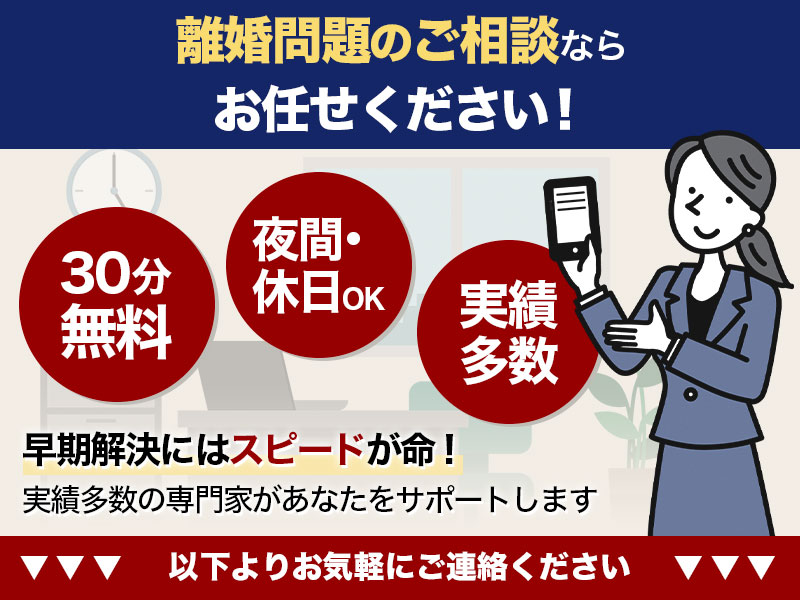
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。