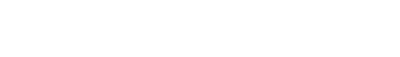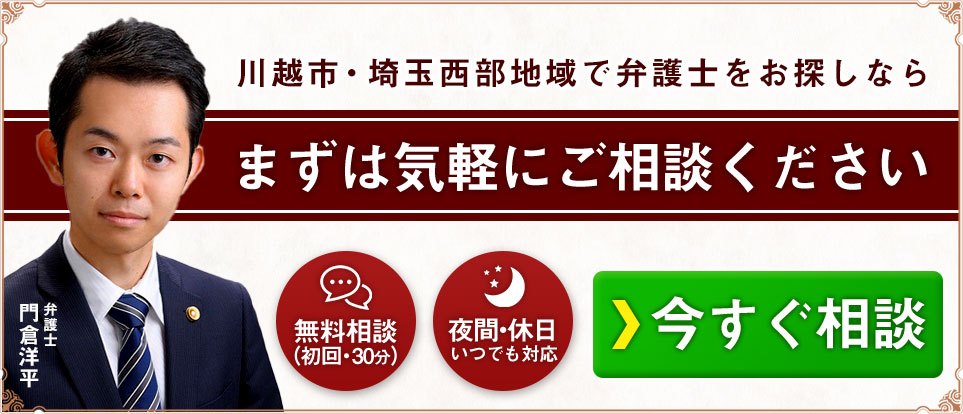選挙のたびに話題にのぼる「選挙違反」や「選挙活動のルール」。
これらの多くは「公職選挙法」という法律に基づいて定められています。
この法律は、候補者が平等に選挙活動を行えるようにするため、また、有権者の自由な判断を守るためのものです。
本記事では、公職選挙法の基本的な目的やルールをわかりやすく解説するとともに、事前運動の禁止やネット選挙の制限、最近の法改正についても解説します。
選挙をより正しく理解し、有権者としての判断に役立てたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
公職選挙法とは?どんな目的の法律なのか
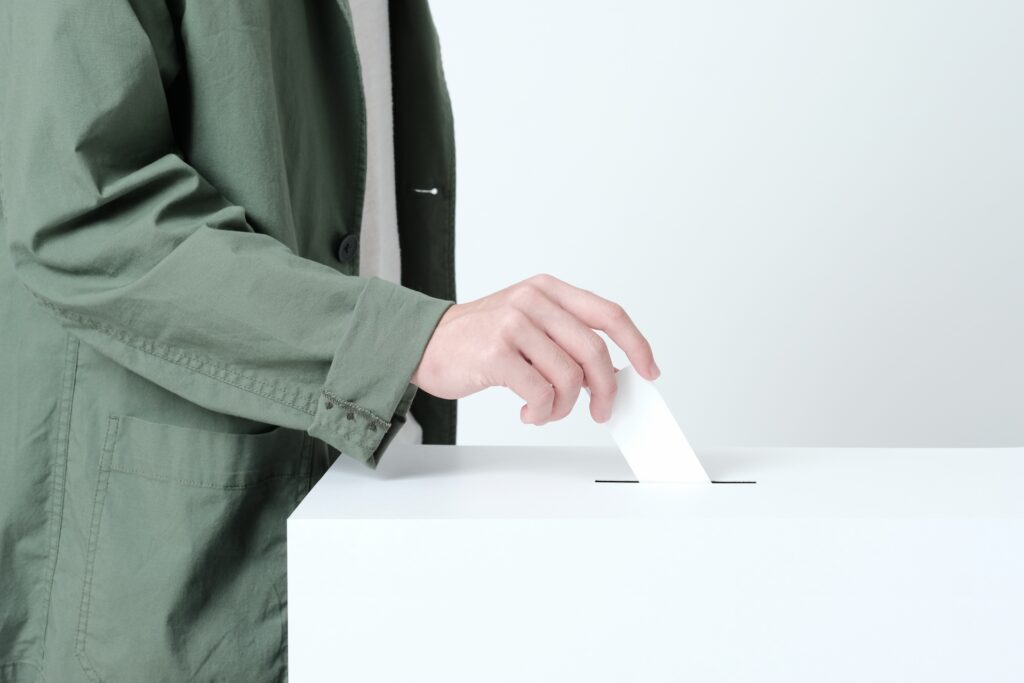
公職選挙法は、国政選挙や地方選挙など、日本で行われる公的な選挙において「候補者」「政党」「有権者」それぞれが守るべきルールを定めた法律です。
公職選挙法がつくられた理由とは
公職選挙法は、戦後の混乱期における選挙の買収や不正行為を防止する目的で、1950年(昭和25年)に制定されました。
制定以前の選挙では、お金や物で票を買う行為が横行しており、民意を歪める深刻な問題となっていたのです。
こうした不正を防ぎ、誰もが公正に立候補し、有権者が自由に意思を表明できる環境を整える目的で制定されたのが公職選挙法です。
選挙のルールを決めることで何が守られるのか
選挙ルールを法律で明確に定めることで、以下のような民主主義の根幹が守られます。
まず、候補者にとっては「公平な競争の場」が確保されます。
資金力や組織力のある一部の候補が有利になりすぎないよう、活動時期や手段が制限されているのです。
次に、有権者にとっては「自由な判断と投票の権利」が守られます。
買収や脅迫などにより意思を歪められないよう、選挙運動に一定の規制が加えられています。
公職選挙法で定められている主なルール

公職選挙法には、選挙の公正を守るためのルールが定められています。候補者・政党・有権者のすべてに関わるため、選挙に関心を持つのであれば知っておきたいポイントです。
選挙前の活動はどこまで許される?事前運動の禁止
公職選挙法では、選挙の「告示日(国政選挙では公示日)」より前に選挙運動を行う「事前運動」が禁止されています。
選挙運動とは
「特定の候補者に対して投票を呼びかける活動」を意味し、ビラ配りや街頭演説、電話による投票依頼などが該当します。
- 選挙が正式に始まる前に「○○さんに投票してください」とチラシを配布する
- 選挙が正式に始まる前にSNSで特定の候補への投票を呼びかける
ただし、単に政策を紹介したり、日常的な政治活動の一環として活動報告を行ったりは許されているため、「どこからが事前運動か」を見極めることが重要です。
お金や物で票を集める行為は禁止
いわゆる「買収」にあたる行為も公職選挙法では厳しく禁じられています。
買収として違法にあたる事例- 有権者に対して現金を渡す
- 有権者に対して食事をごちそうする
- 有権者に対して物品を配る
- 陣営スタッフに対して相場を超える報酬を支払う
- 選挙ボランティアに交通費を過剰に支給する
こうした違反があった場合は、当選無効や刑事罰の対象になるため、候補者・支援者ともに十分な注意が必要です。
ネットでの選挙活動にはどんなルールがあるのか
2013年の法改正により、インターネットを使った選挙運動(いわゆる「ネット選挙」)が解禁されました。 ただし、自由に発信できるようになった反面、ルールも存在します。
まず、選挙運動に使えるのは「選挙期間中」に限られており、それ以前にSNSで投票を呼びかけると事前運動に該当する可能性があり、注意が必要です。
また、候補者本人や政党以外の第三者が誹謗中傷を投稿したり、なりすましアカウントを作成したりすることも禁止されています。
さらに、有料広告(リスティング広告やバナー広告など)は、候補者や政党以外の者は利用できず、SNSでの拡散にも注意が必要です。ネット上でも、公職選挙法による「公正性の確保」が強く意識されていることがわかります。
-

-
公職選挙法でSNSにやってはいけないこととは?違反事例と注意点をわかりやすく解説
選挙のたびに話題となる「公職選挙法」ですが、近年ではSNSの普及により、知らないうちに法律違反にあたる投稿をしてしまうケースが増えてきています。 特に選挙に関心の高い若年層や、18歳で新たに選挙権を得 ...
続きを見る
最近の話題になった事例と法改正の流れ

公職選挙法の規定は長年にわたり大きく変わらないままでしたが、近年のSNSの普及や選挙戦術の多様化により、現行ルールでは対応しきれない事例が相次いでいます。
都知事選で話題になった「ポスタージャック」
2024年の東京都知事選では、選挙ポスター掲示板を「ジャック(占拠)」するという前例のない事例が発生しました。
複数の候補者を擁立する政党が寄付を募って、支援者には計24人分の掲示板にオリジナルのポスターが貼れるという呼びかけをしたのです。
その結果、同じデザインのポスターが24枚並ぶという異例の事態に発展しました。
公職選挙法上は違法とされませんでしたが、掲示板の目的である「候補者の選挙情報提供」を逸脱し、有権者の公平な判断を妨げかねない行為として物議を醸しました。
兵庫県知事選の「2馬力選挙」って何が問題だった?
2024年の兵庫県知事選では、ある候補者が当選を目的とせずに選挙活動を展開し、「2馬力選挙」として注目を集めました。
問題となったのは、特定の候補者を支持するためだけに、別の候補者が立候補していた点です。
言い換えれば、選挙カーも運動員も2倍になるということ。
選挙の公平性が損なわれているのでは?と疑問視する意見も多く、注目を集めることになりました。
ルール見直しは進んでいる?総務省の動き
上記のような事例を受けて、総務省では公職選挙法の一部見直しに向けた検討が進められています。
特に「ポスター掲示の在り方」や「候補者乱立による制度悪用」、「ネット選挙の透明性の確保」などがテーマとして挙げられています。
まだ具体的な改正には至っていませんが、現代の選挙環境に即した法整備の必要性が広く認識されつつあり、今後の動向が注目されています。
選挙のルールを知って正しく参加しよう
公職選挙法は、選挙の公正さを保ち、私たち一人ひとりの「一票」の価値を守るために定められた法律です。
事前運動の禁止や買収の防止、ネット選挙のルールなど、多くの規定が存在するのは、自由な選挙と民主主義を健全に機能させるために欠かせないためです。
一方で、近年の選挙ではポスタージャックや選挙運動のグレーゾーンを突いた事例も見られ、制度の見直しが必要とされる局面も増えてきました。
正しい知識をもとに選挙に参加することは、社会を動かす第一歩です。
しかし、知らずに公職選挙法に違反してしまった、あるいは違反を指摘されてトラブルに発展してしまったというケースも少なくありません。
「もしかして違反してしまったかも」「通報されてトラブルに巻き込まれた」といった方は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士のアドバイスを受けることで、適切に対応できる可能性が高まるでしょう。