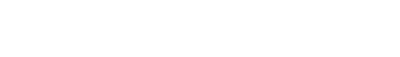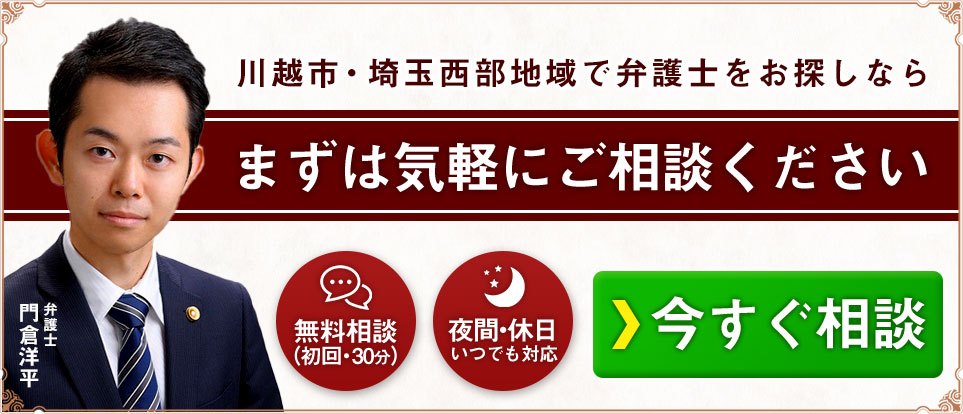昨今、スマートフォンなどの予備電源として、モバイルバッテリーを持ち歩くのは当たり前になりました。
しかし、飛行機内や電車内でモバイルバッテリーが発火し、車両が停車したり、乗客が避難したりする事態も実際に起きています。
もし、その原因が「自分のモバイルバッテリー」であったと考えると、不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、モバイルバッテリー火災が起きる原因や、飛行機・電車での最新の持ち込みルール、万が一火災の原因となってしまった場合の民事・刑事上の責任、そしてトラブル時の対処法についてわかりやすく解説します。
なぜモバイルバッテリーが火事を引き起こすのか?

モバイルバッテリーは、スマートフォンなどをどこでも充電できる一方で、使い方や環境を誤ると発煙・発火につながるリスクを抱えています。
特に、機内や電車内のように密閉された空間では、小さな火でも大きなトラブルに発展しかねません。
モバイルバッテリーが発火する主な原因
市販のモバイルバッテリーの多くには、リチウムイオン電池やリチウムポリマー電池が使われています。
これらはエネルギー密度が高い一方で、異常が起きると「熱暴走」と呼ばれる急激な発熱・発火につながることがあります。
熱暴走が起こる代表的な原因としては、次のようなものが挙げられます。
- 落下や強い衝撃で内部の電池セルが損傷する
- 直射日光の当たる車内など、高温環境に長時間放置する
- 水濡れや結露によって内部でショートが起きる
- 基準を満たさない粗悪品・模倣品を使用する
こうした異常が重なると、内部でガスが発生して膨らんだり、焦げ臭い匂いや白煙が出た後に炎が上がったりなど、短時間で危険な状態に至るおそれがあります。
機内や電車内で起きた過去の事故例
モバイルバッテリーが発火すると、機内や電車内では車両の停止や避難誘導など、大きな影響が出るおそれがあります。ここでは、近年報道された事例について簡単にご紹介します。
- JR山手線の車内でモバイルバッテリーが出火した事例
2025年7月、JR山手線を走行中の電車の車内で、乗客が所持していたとみられるモバイルバッテリーから火が上がりました。乗客数名が軽症を負ってしまい、火は車内に備え付けの消火器で消し止められたとされています。モバイルバッテリーはリコール(メーカー側が無償で回収・交換などに対応する制度)の対象商品でした。
(参照:山手線内でモバイルバッテリー突如発火!)
- 福岡発仁川行き旅客機内でモバイルバッテリーから煙が出た事例
2025年9月には、福岡発・韓国仁川行きのイースター航空の機内で、乗客が手にしていたモバイルバッテリーから煙が発生したと報じられました。客室乗務員がすぐに消火器などで対応し、火は機内で鎮圧され、乗客に大きな被害は出なかったとされています。
このように、モバイルバッテリーのトラブルは、鉄道・航空を問わず、国内外の公共交通機関で現実に起きています。
ひとたび事故が起きると多くの人の安全や運行に影響するため、「自分のバッテリーが原因になり得る」という意識を持って慎重に取り扱いましょう。
飛行機・電車でのモバイルバッテリーの持ち込みルール

モバイルバッテリーに使われるリチウムイオン電池は、異常が起きた際に発煙・発火するおそれがあることから、航空機などでは「危険物」として扱われ、通常の荷物とは別にルールが定められています。
航空機内持ち込みの基本ルール
飛行機では、モバイルバッテリーは「預け入れ不可・機内持ち込みのみ」が大原則です。
具体的なルールとしては、以下が挙げられます。
- 受託手荷物に入れて預けることはできず、手荷物として客室内に持ち込むこと
- 100Wh(ワット時定格量)以下のモバイルバッテリーは機内持ち込み可
- 100Whを超え160Wh以下のものは、個数制限や事前の航空会社の承認が必要
- 160Whを超える大容量は、原則として旅客機への持ち込み・預け入れとも禁止
(参照:日本航空|特にお問い合わせの多い危険物の代表例)
2025年7月から変わったポイント
2025年7月8日からは、日本国内線・日本の航空会社を中心に、機内でのモバイルバッテリーの「置き方」についてもルールが変更されました。
国土交通省の広報によると、以下を協力要請として新たに講じています。
- モバイルバッテリーを座席上の収納棚に収納しないこと。
- 機内でのモバイルバッテリーから携帯用電子機器への充電または機内電源から。
- モバイルバッテリーへの充電については、常に状態が確認できる場所で行うこと。
収納棚の中で発煙・発火した場合、乗客や客室乗務員が異変に気づくのが遅れ、初期対応が遅れてしまうリスクがあります。
そこで、「持ち込みはOKだが、自分の目の届く場所で管理する」という方向にルールが強化されたとイメージしておくとよいでしょう。
電車・バスでは禁止されていないが注意は必要
一方、鉄道や路線バスでは、モバイルバッテリーそのものの持ち込みを一律に禁止する全国的なルールは現時点では公表されていません。
多くの鉄道会社では、モバイルバッテリーはスマホなどと同様に手回り品として扱われており、車内への持ち込み自体は認められています。
ただし、国や自治体、事業者は、発火事故を受けて次のような点に注意喚起をしています。
- リコール対象品や明らかに膨張・変形しているバッテリーは使用しない
- 座席の下や荷物棚など、目の届かない場所で長時間充電しない
- 衝撃や水濡れ、高温環境を避けて持ち運ぶ
電車・バスでは「全面禁止」ではないものの、利用者側の自己管理が強く求められているのが現状です。
旅行や出張の際は、航空会社や利用する交通機関の最新ルールを事前確認することを心がけておきましょう。
火事の原因が自分のモバイルバッテリーだった場合の持ち主の責任

モバイルバッテリーが原因で火災が起き、その持ち主が特定された場合、「どこまで責任を取らないといけないのか」が問題になります。
法律上は、大きく分けて「民事上の損害賠償」と「刑事責任」、そして場合によっては「メーカー側の責任」が絡んできます。
民事上の損害賠償責任
まず考えられるのが、民法上の「損害賠償責任(不法行為責任)」です。
モバイルバッテリーの管理が不適切だったこと(例:明らかに膨らんでいたのに使い続けた、破損品と知りつつ持ち歩いた、容量制限を無視して機内に持ち込んだなど)が原因で火災が発生し、鉄道会社や航空会社、他の乗客に損害が生じた場合、持ち主はその損害を賠償しなければならない可能性があります。
想定される損害の例としては、
- 車両や機体の修理費用
- 運休や遅延による事業者側の損失
- けがをした乗客の治療費や慰謝料
などが挙げられます。
刑事責任を問われる可能性
火災で人がケガをしたり、大きな被害が出たりした場合は、民事だけでなく「失火罪」などの刑事責任が問題となる可能性もあります。
【刑法第116条】
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(引用:刑法 | e-Gov 法令検索)
たとえば、
- 発火の危険性が高いことを繰り返し注意されていたのに無視して使用し続けた
- 禁止されている改造や粗悪な互換部品を用いていた
といった状況では、失火罪と判断されるリスクが高まるでしょう。
実際に刑事事件として立件・起訴されるかどうかは、被害の大きさや悪質性、本人の事情などを踏まえて総合的に判断されます。
「モバイルバッテリーが燃えた=必ず刑事責任」というわけではありませんが、刑事責任に発展し得る可能性は意識しておくべきです。
メーカーや販売店が責任を負うケースとの違い
モバイルバッテリー火災では、「利用者の使い方」に問題があるケースだけでなく、「製品自体の欠陥」が原因となるケースもあります。
この場合は、いわゆる製造物責任法(PL法)などに基づき、メーカーや販売店が損害賠償責任を負う可能性があります。
たとえば、
- 取扱説明書どおりに使用していたにもかかわらず、内部構造の欠陥で発火した
- リコール対象製品であるのに、適切な周知・回収措置がとられていなかった
といった場合には、利用者側の責任は限定的であり、メーカー側の責任が中心になることが考えられます。
ただし、膨張・破損した状態のまま使用していたり、禁止されている環境で使用・保管していたなど、利用者側の注意義務違反が大きい場合は、メーカー責任が認められにくくなったり、賠償の一部を負担しなければならない可能性もあるため注意しなければなりません。
モバイルバッテリー火災の原因・責任を理解して安全に利用しよう
モバイルバッテリーは、日常生活や旅行の心強い味方である一方で、使い方や保管方法を誤ると、発煙・発火といった重大な事故につながるおそれがあります。
万が一、火災や発煙などのトラブルに巻き込まれた、あるいは自分のモバイルバッテリーが原因だった可能性がある場合には、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、事故の状況や製品の状態などを踏まえて法的な責任の有無や範囲を整理し、相手方との交渉や賠償請求への対応方針について、具体的なアドバイスをしてくれます。