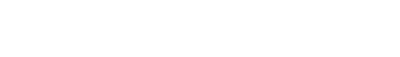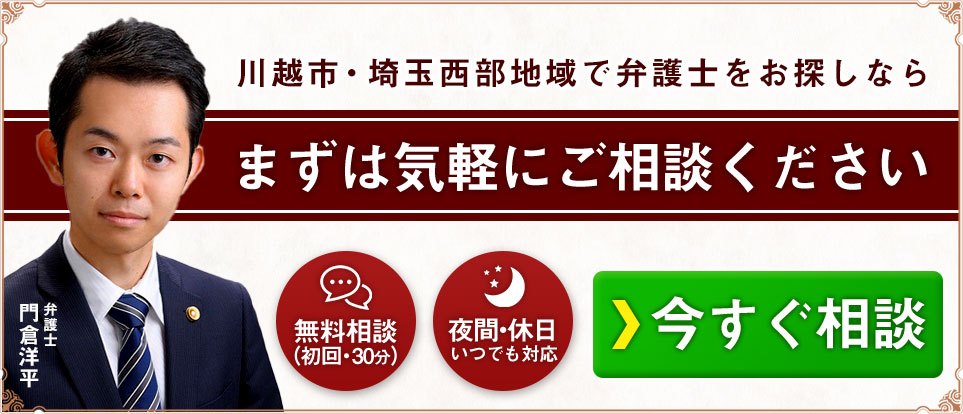自転車での飲酒運転は「ちょっとだけなら…」と軽く考えられがちです。
しかし、道路交通法上はれっきとした違法行為であることをご存知でしょうか。
実は、2024年11月の法改正により、自転車の酒気帯び運転にも厳しい罰則が適用されています。
本記事では「酒気帯び」と「酒酔い」の違いから、検挙時の流れ、罰則や周囲の責任、さらには検挙されてしまった場合の流れまで詳しく解説します。
-

-
【自転車】道路交通法改正2026年のまとめ!青切符は16歳以上から?違反と反則金は?
2026年に施行される道路交通法の改正では、自転車に関するルールが大きく変わります。 これまで注意や警告にとどまっていた交通違反に対し、反則金を科す「青切符」の制度が適用されるほか、自動車が自転車を追 ...
続きを見る
自転車でも酒気帯びは処罰対象
自転車は手軽な移動手段として多くの人に利用されていますが、飲酒後の運転は道路交通法上の酒気帯び運転・酒酔い運転にあたり、例外なく処罰の対象です。
自転車は『軽車両』に分類され、車両として法的に扱われるため、「自動車ほど危険ではない」という理由で見逃されることはありません。
「酒気帯び」と「酒酔い」の違い
道路交通法施行令第44条によると、呼気中アルコール濃度が0.15mg以上であれば「酒気帯び運転」とされます。
一方で、アルコールの影響でまっすぐ歩けない、会話や運転操作に支障が出ると判断されると「酒酔い運転」として、より重い処罰の対象です。
自転車もこの区分に準じて取り締まりが行われ、特に酒酔い運転は事故につながる危険性が極めて高いため、厳しく処罰されるため注意しなければなりません。
「少量ならOK」「歩道なら大丈夫」は誤解
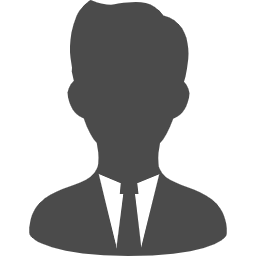
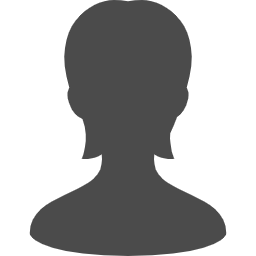
といった声を耳にすることがありますが、これは誤解です。
アルコールは体格や体質、飲酒量にかかわらず反応速度や判断力に影響を与えるため、少量であっても酒気帯びと判断されることがあります。
また、自転車は歩道を通行できる場合があっても道路交通法上は車両の一種であり、飲酒していれば場所を問わず違反行為となるため注意が必要です。
酒気帯び運転の罰則と注意点
 自転車であっても飲酒運転は刑事罰の対象です。
自転車であっても飲酒運転は刑事罰の対象です。
ここでは、運転者本人に科される処罰だけでなく、周囲に及ぶ責任や行政処分との関係について見ていきます。
運転者に科される罰則
2024年の道路交通法改正によって、自転車の酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。
また、酒酔い運転と認定される場合には、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と、より重い刑罰が科される可能性があります。
さらに、刑事罰は前科として記録されるため、「自転車だから大丈夫」という認識は誤りです。
アルコールが確認されれば、形式上は自動車運転と同等のリスクを背負うことになります。
周辺者の責任と注意点
罰則は運転者本人だけにとどまりません。
飲酒していると知りながら自転車を提供した場合には、運転者と同等の罰則が科される可能性があります。
たとえば、
- 飲酒運転を助長する行為
- 酒類を提供
- 飲酒した自転車運転者に同乗
などの行為も処罰対象で、こちらは2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。
仲間同士の軽い気持ちが原因で、提供者や同乗者まで処罰対象になるケースもあり得るため、「自分は運転していないから安心」という考え方は危険です。
-

-
川越で飲酒運転をして逮捕されたら?すぐ弁護士に相談しよう
今年1月7日、川越市で玉突き事故を起こした医師が飲酒運転の疑いで逮捕されました。さらに、同月28日にも温泉施設の駐車場で車に衝突した会社員の男性が酒気帯び運転の疑いで警察に逮捕されています。 このよう ...
続きを見る
行政処分・免許点数との関係
自転車の酒気帯び運転は、自動車やバイクの免許点数制度の対象外とされています。
したがって、原則として免許の点数が加算されることはありません。
ただし、飲酒状態で自転車に乗り重大な事故を起こした場合には、危険運転や過失致傷などの観点から免許停止などの行政処分が科される可能性もあります。
特に自転車と歩行者の事故は損害賠償額が高額化する傾向にあるため、刑事罰だけでなく、民事責任が連動して発生することを強く意識しておく必要があります。
どこから違反?酒気帯びの判断のされ方と検査
 具体的にどのくらい飲んだら違反になるのかというのは、多くの人が気になるポイントです。
具体的にどのくらい飲んだら違反になるのかというのは、多くの人が気になるポイントです。
自転車の酒気帯び運転も、自動車と同様に呼気中アルコール濃度や挙動を基準に判断されます。
ここでは実際の検査方法や、その後の流れを確認しておきましょう。
検問・職質で見られる点と呼気検査
警察官は夜間や繁華街周辺での職務質問、交通取締りの一環として自転車利用者に対しても飲酒の有無を確認します。
特に、顔の赤み、ふらつき、言動の不自然さなどが確認されれば、その場で呼気検査を求められることになるでしょう。
呼気検査を拒否した場合の罰則
「検査に応じなければ証拠が残らないのでは」と考える人もいますが、呼気検査の拒否自体が道路交通法違反となります。
自転車の場合も同様で、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法第118条の2)。
また、拒否の態度はその後の捜査や裁判において不利に働きやすく、酒気帯びの疑いを強める要因となるため、現実的にはリスクを増やす行為でしかありません。
検挙後の流れ(書類送検・略式)と前科リスク
自転車の酒気帯び運転で検挙された場合、手続きは次のように進みます。
- 現場での対応
現行犯逮捕または任意同行となり、警察署で取調べを受ける。 - 検察庁への送致(書類送検)
作成された調書や証拠資料が検察庁に送られる。 - 起訴の判断
軽微なケースでは略式起訴とされ、裁判所が罰金刑を言い渡すことが一般的。 - 刑事処分の確定
罰金刑であっても刑事処分に変わりはなく、前科として記録が残る。 - 刑事裁判の可能性
過去の違反歴などによっては刑事裁判に進み、より重い刑罰が科される場合もある。
酒は飲んだら乗らない!いざというときは弁護士へ
自転車であっても酒気帯び運転は道路交通法違反であり、検挙されれば刑事処分や前科という重いリスクを伴います。
飲酒後に「少しなら大丈夫」と思っても、呼気検査の結果次第で即座に処罰対象となる可能性があります。
一番の予防策は、シンプルに「飲酒した日は自転車に乗らない」という判断を徹底することです。
公共交通機関を利用するなど、代替手段を選ぶことでリスクを未然に防げます。
それでも万が一検挙されてしまった場合は、独断で対応せず弁護士に相談するのが安心です。
専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを踏み、過度な不利益を避けられる可能性があります。
「自転車だから大丈夫」と油断せず、改正道路交通法を正しく理解し、迷ったときは「乗らない」選択をすることが、安全で安心な日常につながるでしょう。