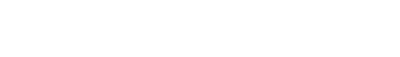コロナ禍で在宅時間が増えるとともに、新たにペットを飼い始める人が増えています。
でも国民生活センターのデータによるとペット関連のトラブルも増えており、トラブルにならないか心配という人は多いのではないでしょうか。
この記事では、様々なペットに関連するトラブルと法律の考え方を事例を交えて解説していきます。
参考国民生活センター PIO-NETに登録された相談件数の推移
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/pet.html
ペット禁止の賃貸住宅でペットを飼育していたら
 ペットを飼いたい人は多くても、「ペット可」の賃貸物件はまだまだ少ないのが現状です。
ペットを飼いたい人は多くても、「ペット可」の賃貸物件はまだまだ少ないのが現状です。
入居時の賃貸借契約で「ペット不可」とされているのに飼ってしまった場合、賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりする可能性はあるのでしょうか。
賃貸借契約と「信頼関係破壊の法理」
賃貸人としても、ペットを飼ったというだけでは解除できません。
- 何度も注意しているのに聞いてくれない
- 他の住人から苦情がきている
など、賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊するような状況がなくては賃貸借契約を解除することはできません。
これを「信頼関係破壊の法理」と言います。
アパートやマンションの賃貸借は長期間にわたって継続することが予想されるので、賃貸人と賃借人は信頼関係で結ばれて契約を交わしています。
賃借人は住居の使い方として想定される範囲で住居を使うだろうと信頼されて契約しているのです。
事例:フローリング貼替費用46万5千円、諸経費3万円を認めた裁判
ペット禁止のマンションで、賃貸人に無断で兄を同居させ兄の飼い犬を室内で飼育していた事案です
ベランダから糞尿の異臭がする、深夜に鳴き声がうるさいなど近隣から再三のクレームがありました。東京地裁はフローリング貼替46万5千円、諸経費3万円を認めました。
ペット関連の近隣トラブル・散歩中のトラブル
 ペットを飼っていると、ペットの鳴き声がうるさい、あるいはニオイ・糞尿が迷惑、ペットの毛が洗濯ものに付着するなど、近隣住民からクレームがくることがあります。
ペットを飼っていると、ペットの鳴き声がうるさい、あるいはニオイ・糞尿が迷惑、ペットの毛が洗濯ものに付着するなど、近隣住民からクレームがくることがあります。
ペット可のマンションでも十分な注意が必要
ペット可のマンションなどでもペットを飼わない住人も多いので、周りの住人に迷惑をかけていないか十分に注意する必要があります。
新たに入居するときは、あらかじめ
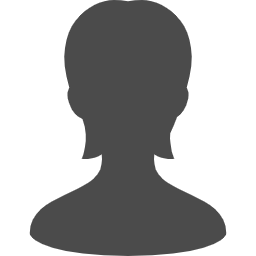
などと隣近所に挨拶しておくとよいでしょう。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第7条1項では、動物の所有者・占有者の動物愛護・管理に関する責任を定めています。
また、動物の種類・修正に応じて適正に飼育すること、健康・安全の保持、動物が人の迷惑にならないように努める責任を明記しています。
飼い主の損害賠償義務および裁判事例
民法718条1項により、ペットの飼い主には第三者に生じた損害を賠償する義務があります。
民法718条1項
- 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
飼い主が「相当の注意」をもってペットを管理していたことを証明できれば責任を免れるわけですが、なかなか認められないのが現状のようです。
注意しないといけないのは、ペットを預かった者、借りた者も同様に責任を負わなくてならないことです。
旅行に行くときなど気軽に知人にペットを預かってもらったりしますが、重要な責任を伴うことを知っておきましょう。
事例①:鳴き声被害で1人30万円の慰謝料
マルチーズやシェパードの鳴き声が連日の深夜・早朝にわたり神経衰弱に陥った近隣住人が、飼い主に対して慰謝料を請求した事件です。
横浜地裁は、飼い主が保管義務を怠ったこと、推測される被害の程度を大きく超えるものであったことを理由に、1人につき慰謝料30万円を認めました。
事例②:ペットを避けて転倒 1,280万円の損害賠償
ランニング中の男性が飛び出してきた犬を避けようとして転倒・骨折したという事件がありました。
大阪地裁は「散歩させる際に、犬をつないでおく注意義務を怠った」として飼い主に対して1,280万円の支払いを命じました。
ペットの負傷・死亡トラブルで損害賠償金・慰謝料を請求できる?
 ペットが負傷または死亡したときに、相手方に責任があるのであれば損害賠償や慰謝料を請求できます。
ペットが負傷または死亡したときに、相手方に責任があるのであれば損害賠償や慰謝料を請求できます。
ペットが死亡した場合はペットの時価、飼い主の慰謝料、葬儀費用などが請求の対象となりますが、人間と異なりいずれも数万円程度の少額になることが多いようです。
ペットは物?法律の考え方
ペットは法律上「物」として扱われます。
生き物ですが人間ではないので財産と考えられているのです。
それでも、生き物としての側面は無視することはできません。
被災地ではペットの救助に向かうといったニュースも聞かれます。
反面どんなに高額でも「宝石の救助に向かう」というのは聞いたことがありません。
社会的にもペットに対する考え方は変わってきていると言えます。
法律上、ペットが物とは違う扱いを受ける例としては、動物愛護法で「愛護動物」として扱う規定があります。
2020年に施行された改正動物愛護法では、
愛護動物をみだりに殺傷した者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処す
とされています。
これはペットを単に「物」として扱うなら適用される器物損壊罪の
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
にくらべて格段に重くなっています。
動物愛護の考え方が浸透してきているといえるでしょう。
ペットの医療過誤および裁判事例
ペットを獣医師に診せたが、医療ミスで治療費がかさんだり、ペットが亡くなった、などという事故もあります。
獣医師も人間の医師と同様に下記のような義務を負っています。
- 診療を頼まれたら断ってはいけない(応招義務)
- 善良な管理者の注意義務をもって診療を行わなければならない(善管注意義務)
- 病状等を説明しなくてはならない(説明義務)
獣医師が義務を怠ってペットを死傷にいたらせた場合は、飼い主は獣医師の法的責任を問うことができます。
事例:診断の義務違反で獣医師に約59万円の支払い命令
8歳のメスの秋田犬が陰部の出血などで動物病院で受診(2014年5月14日~7月18日)、膀胱炎と診断されましたが、7月29日に別の救急動物病院で死亡した事案です。
獣医師には遅くとも7月18日に子宮蓄膿症かどうかを診断する義務があったと指摘。
「血液検査などを行わず、経過観察にととめたことは診断の義務に違反した」として獣医師側に慰謝料40万円と治療費約15万円、葬儀費用3万8千円の支払いを命じました(福岡地裁)。
ペットの葬儀でのトラブル
ペットが亡くなったときもトラブルの多いタイミングです。
ペット専用の葬儀業者が火葬車でペットを火葬した際に、ニオイ・粉塵・煙が原因で近隣とトラブルになる事例がよく報告されています。
弁護士に相談するメリット
このようにペットのトラブルは多岐にわたり、注意していても避けられない事故もあります。
裁判にまで発展する事例も多く、飼い主の責任は重大といわざるを得ません。
また、医療過誤のように飼い主が被害者となる場合もあります。
ペットのトラブルで請求できる慰謝料は数万円というのが多く、弁護士費用に見合わないこともあります。しかし、ペットへの愛情はお金に換算できません。
また、ペットは人間ではないのでペットに財産を遺すことはできませんが、負担付遺贈によってペットの世話をしてくれる人に財産を遺すことは可能です。このような手続も専門家である弁護士に任せると安心です。
弁護士に相談するメリットは次のようなものがあります。
- トラブルの相手方と直接対峙する必要がない
- 法律的な手続を弁護士が代行する
- 相手方との交渉から法廷での対応まで一貫して任せられる
- ペットのために相続での対処を依頼できる
- 弁護士は依頼人の味方になって対処法を考える
ペットのトラブルでお悩みのときは弁護士にご相談ください。
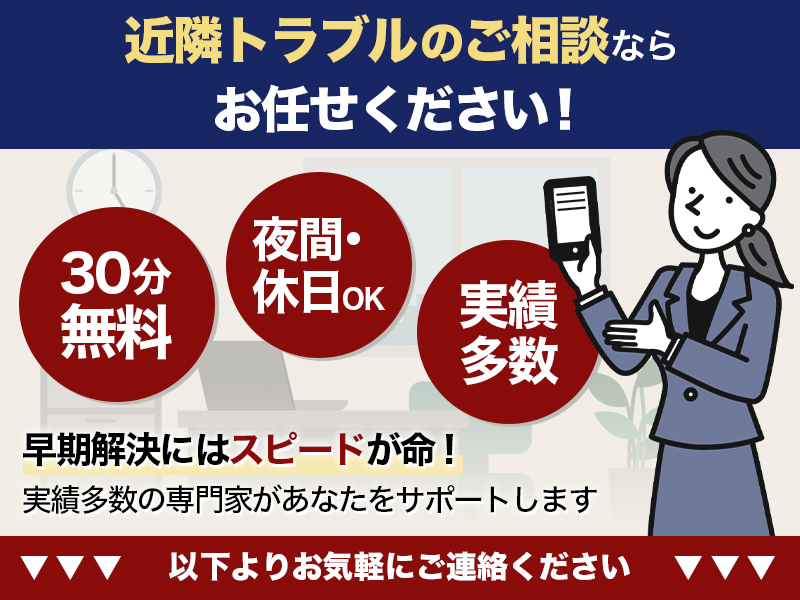
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。